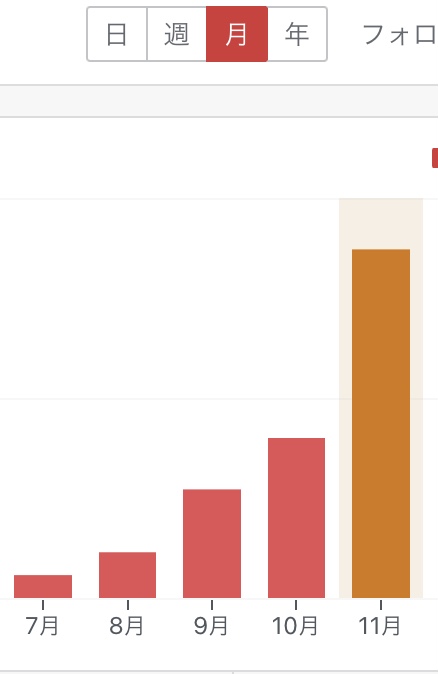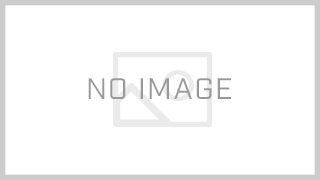突然だが、
男は同期の「くまちゃん」と共に、大宮駅から長野新幹線に乗り換え、胸中の不安を抑えながら軽井沢へと向かっていた。
車窓に何の気なしに映る風景には、すでにコンクリート状の人工物はほとんどなくなり、翠緑ばかりが広がっている。
長野県軽井沢町と言えば、広大な自然と四季折々の景観に恵まれた避暑地として名高い。
高原に位置するために、避暑、あるいは別荘地として古くからリゾート利用されてきたことは改めてお伝えするまでもないだろう。
しかしながら、新卒3年目を迎える二人の会社員が、当該の高級リゾートエリアへとその物理的距離を縮めているのは、休暇のためにではなかった。
「研修」である。
社が軽井沢に設けている、噂に名高い「訓練施設」における研修である。
それは、日常の社内研修とは一線を画した、”ふつうではない通過儀礼”として語り草にされることが往々にしてあった。
ふつうではない、の中に、高揚感とも恐怖心とも取れない、異様な感情が混ざった状態で、所属長や直属の先輩が「施設」のことを語るのを男は日ごろ目にしていた。
 男にとって、開業して10年経ったばかりの長野新幹線を利用するのはこの時が初めてであった。
男にとって、開業して10年経ったばかりの長野新幹線を利用するのはこの時が初めてであった。
「くまちゃん、何がどうなるのかね?」
到着まであと20分。軽井沢が近づいて来る。
男は、最前からの不安を胸の中にしまっておくことの息苦しさに耐えかねたのか、聞いてどうなる風でもない、実にあいまいなクエスチョンを言葉にしてみた。
「くまちゃん」と呼ばれたもう一人の細身の男は、彼にとって同期であり、60人近い新卒社員の中で、入社式後の研修で何となく座席が近かったことから何となく仲良くなった、いわゆる同期のダチであった。
何より気がおけない人物であったし、指導する学年や科目もかぶるものがあった。
新卒未経験で受験指導の業界に採用され、右も左もわからなかった男にとって、学生バイト時代からその会社での勤務経験があり、自分より指導経験上の先輩である「くまちゃん」は、自信に満ちた頼りがいのある存在であった。
「おれにもわかんね」
「くまちゃん」(ここからはそう呼ぶ)は、前方の一点を見つめたままで表情を崩すことなく、実にドライな声色で返答した。
語尾は「わかんね」で切るとも、「わかんねー」と伸ばしているとも言い切れない長さだ。
「・・・そうよな」
会話は続かなかった。
疑問を投げかけても、これから起きることが何ら解決されるわけではない。
男は、「この先」に関する言葉を発してしまったことが、何やら妙に恥ずかしく感じた。
「そうだよね」
同じようなフレーズを繰り返して口に出しはしたが、2度目には、1度目の自らの言葉を打ち消すような響きを込めた。
同時に、好意的に感じていない今の所属長が、したり顔で、
「何かを準備しようとして臨まないことだね、魁くん・・・いってらっしゃい」
と反応に困る送り出しの言葉をくれたことが頭によぎった。
そのベッタリとした笑顔の不快感と、その送り出しの際の発言に今の奇妙な恐怖心を見透かされたかのような違和感が加わった。
なるようになる。
自身にとって、あまり強い説得力を得られる格言ではなかったが、何も起きていないうちから心理的に追い詰められていた男は、考えがまとまらないままそれを心中で繰り返し、すがることにした。
なるように、なる。(きっと)
*
開放的な雰囲気の軽井沢駅に、速度を緩めて新幹線は停止した。
日差しは適度に出ていて、強風でない程度に風がある。
「あー、研修じゃあないときに来たかったあー」
先ほどのドライな応答とは別人のように、くまちゃんがやや大きな声を出した。
魁はあまり旅行して回るタイプではないし、軽井沢にそこまでの興味関心を抱いてはいなかったが、その時はくまちゃんの独白に少し共感した。
何しろ周囲はカジュアルな服装の衆人たちが、さあバケーションを楽しもう、あるいは楽しんでいるさ中、あるいは十分に満喫して名残惜し気に地を去ろうとする風景ばかりである。
「訓練所」までは会社負担でタクシー移動をすることになっている。
平日の日中であったが、タクシーはすぐに捕まえられた。
訓練所の固有名詞(仮にパレスとする)を出したくまちゃんが、
「場所わかりますか?」
と確認を入れる前に、タクシーの運転手が即答した。
「あーパレスね。大変だね」
二人は一瞬硬直し、顔を見合わせるようなリアクションも取らないままに座席に乗り込んだ。