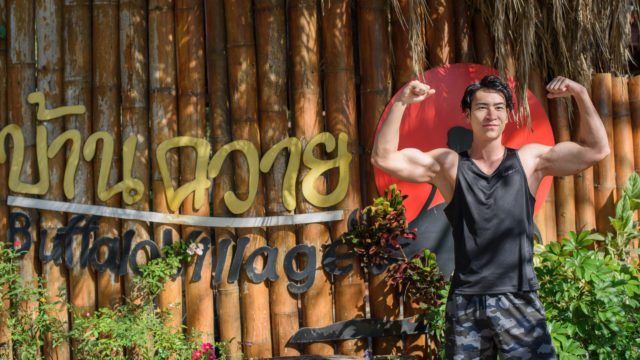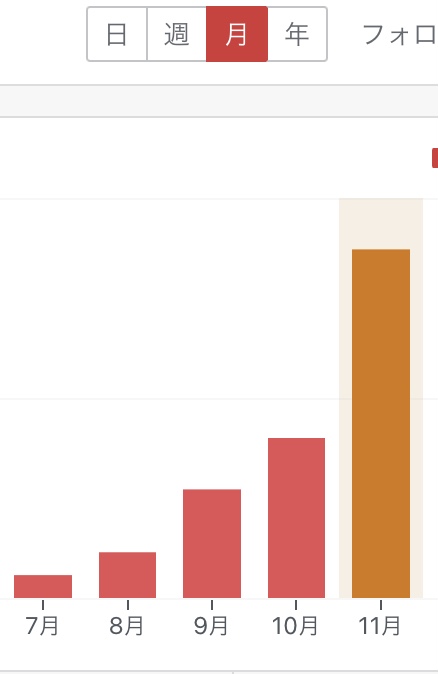突然ですが、
古くからのことわざに「無くて七癖」という言葉がありますね!
「クセ(特徴的な行動)がないように思われる人であっても、よく見ると7つ以上のクセを持っているものだ」
といった意味かと記憶していたので、コトバンク様で確かめたら、大体合致していました。
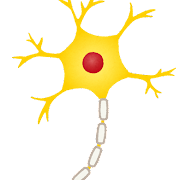 皆さんの脳内にあるニューロンです
皆さんの脳内にあるニューロンですさて、
魁がお子さんを指導しているときに気になる、あるいは状況によって直させたいと考える、
あんまりよくない口ぐせ
について記事を書きます。
これを1回や2回口にしたからと言って悪!!ということではありませんで、
習慣的に言ってしまう心構えのまま時間を経ると、学力的に一歩伸び悩んだり、いわゆるダメな大人に近づく可能性がありうるので、お子さんのうちに改善していくべき!
と考えて述べるものです。
大人になって、成長しきってから気づき、時間をもって直すのはたやすいことではありません。
ただし、「成長力や吸収力」を十分持ったお子さんの時期なら、陥らずに質していけると考えます。
*
魁が気になる危うい口ぐせは・・・
・「そうじゃなくて~」「いや」といった否定を伴う接頭句
・「正直~」「言うなら」といった換言
・「あーね」「そっちね」といった了解のフレーズ
の3本です!!
読者さんご自身や、お子さんはいかがですか?
*
人は誰でも、自分のリズムで、気分よく話をしたいものです。
 他人のリズムで、気分悪く話したい!なんて人いますか?
他人のリズムで、気分悪く話したい!なんて人いますか?お子さんも同じです。
ただし、成長期のお子さんに関しては、「自分の言いたいこと」を一旦抑えて、「相手の意見を聞き入れつつ的確に返答する」という、
キャッチボール要素
が思考力、表現力の向上に不可欠です。
高校受験までは、究極、この力の有無で勝負が決まると言って良いです。
赤ちゃんや幼児期でしたら自分の気持ち最優先で、言いたいことを遠慮なく言って回っていても十分OK!!な訳ですが、だんだんそうもいかなくなってきます。
学校の教諭が、
「手を挙げてから発言しなさい!」「挙手のハイは一度!」
等と時には厳しく指導するのも、ここまで考えているかは存じませんが、関連があるからと推測します。
(そのまま大人になるとジュク業界のニンゲンのようになってしまいます)
*
もうお気づきの読者さんもいらっしゃるように、上記の言葉には、キャッチボールができるようになることを阻害する働きがあります。
・「そうじゃなくて~」「いや」といった否定を伴う接頭句
相手の言うことを受け止める < 自分の言いたいことをいつ切り出すか
の状態でいっぱいになっていて、発言するタイミングを計っている「順番待ち」の心理です。
否定語の入った返答を返される方は気分も悪いですが、それよりも深刻なのは、頓珍漢な返答が返ってきて、会話が成り立っているようで成り立っていない恐れがあることです。
もちろんズレた解答をする悪癖なので、テストで「?」な失点が出ます。
・「正直~」「言うなら」といった換言
日本語において、一旦自分が言った表現を、さらにわかりやすく言い換えること(=換言)自体は頻繁に行われます。
最も代表的な言葉は、接続詞(つなぐ言葉)の「つまり」です。
「換言は説明に必要じゃん!何がダメなの??」
という声が聞こえてきそうです。
その通り!換言は大事な日本語の使い方の一つです。
 国語の文章読解のときも、注目が必須!!
国語の文章読解のときも、注目が必須!!これが口癖になっている場合、「換言できる言葉の機能に頼って、話の前後がチグハグになっている」恐れがあるので、魁は注意を払っているのです。
別の言い方をするならば(⇐これも換言)、「換言の表現を使用する以上、話の前後の脈絡がつながっていることが最低条件」ということです。
これをわかっていないで「正直~」「言うならば~」を習慣的に使うお子さん(場合によっては社会人なのに…というケースもありますがw)は、前項の「否定を伴う接頭句」と同じように、
自分が強引に言いたい言葉を発する順番待ち
をしているだけ!という状態にあります。
例えば、極端に書くと、
「私はスポーツマンタイプではない。つまり、インドア派だ」
でしたら、換言の前後がほぼイコールなので、的確な文として成り立っていますが、
「今日の天気は晴れではない。いうなれば(or正直)、昨日の晩飯うまかったなあああ!」
と言った、聞いている相手を置き去りにした展開で話してしまっているとしたら、もはやキャッチボールではなく、暴投大会です。
※実際はここまで無理な構成ではなく、微細なズレであることが多いです。
・「あーね」「そっちね」といった了解のフレーズ
自己保護の心理が見え隠れするので、自分の間違いと向き合えていない恐れがあります。
「それで済まそう」
「本当はわかってたけどね」
というゴマカシ心の声の発露だと考えています。
「あーね」は、正面から自己の間違いに向き合えていない逃げ。
「そっちね」は、ほぼわかっていたけど(あえて)選択しなかったというウソ。
どちらにせよ、次も同系統の間違いが発生する未来が見えます。
間違いに目を向けるのは楽しいことではないし、環境によっては「恥をかく」危険性もあります。
そこから心身を守ろうとするのは、本能的に当然の反応なのかもしれません。
魁は、その言葉をお子さんから耳にしますと、よりしつこく食い下がる様にしています。
(低音で)「・・・ほんと~~~~にわかったんですか?わかったんですね???」
から始まって、言わなきゃよかったレベルの確認が入ります。
*
今回記事にした言葉たちが、危険なクセであるというのは、統計や脳科学的な分析に基づくものではなく、魁が実際に指導していて気を付けている瞬間を文章化したに過ぎません。
ひょっとすると、ただ単に使っていたお子さんが、魁の指導力不足で伸びない時期があっただけかもしれませんし、出会った社会人でこの口ぐせのヤツ自身が、元来ダメ人間だっただけかもしれません!
ただし、社会人の方は修正不可能としても、お子さんの口ぐせについては、突っ込んで尋ねていくと、
「当たってます・・・」
ということが多く、働きかけていけば、そこから軌道修正を図っていくことは十分にできます。
「・・・クセが(若干)強めですね」「・・・一回見たら忘れづらいキャラですね」と言われがちな魁が言うので、間違いございません!
 ○の方に近づいていけるように・・・。では、今日も指導に行ってまいります!
○の方に近づいていけるように・・・。では、今日も指導に行ってまいります!