突然ですが、
読者の皆さん、保護者さん、あるいは教育サービス業界において生活されているそこのアナタは、お子さんから、
「なんで勉強なんかしないといけないの?意味なくない??」
と(おそらくは学習状態がそんなに良くないときに)言われて、どのように答えているのでしょうか?
- 「将来楽になるために今は苦労しておきなさい」
- 「オトクだから」
- 「みんなやってるから」
- 「いいからやれ」
など、都度瞬時に様々な切り返しが求められるはずです。
1は、「じゃあ、父ちゃん母ちゃんは今楽なの??」と追い打ちされると、グッ!?となりかねませんし、「楽しいよ!」と返したとしてそれを信じてくれるか、じゃあボク(私)も同じように勉強やろうかな…と思えるかはお子さん次第でしょうか。
2は、お子さんに届くと思って、割と若めの大人が使ってしまいがちなインスタント表現なのですが、効果は低い部類の言葉で、魁は使いません。
「オトク」=金銭的に得であるという考えがあるからか、自分で仕事をgetして金銭を手に入れる…という勤労の経験がないお子様にはほとんど響かないようです。
3・4は、自分で書いておきながら「こんな言い方する人、現代にいるのか?」と後から思ってしまう言い方です。
「他と揃えないと出遅れる」「つべこべ言うな」と言った過ぎ去りし”ショーワ”の感覚に基づく表現と思いがちですが、世に現存するカイシャの職場においても、内心思っていたり、類似の言葉が飛び交ったりしがちで、それをそのままお子さんに転用してしまうのではないでしょうか。
経営者や上司の脳が旧来のままだと、「お子さんに勉学の何たるかを報せ、導く」等と息巻いている塾ガイシャの中でも、そのような哀しいシーンが展開されます。
 大人ほど、自分がされたことをそのままお子さんに・・・
大人ほど、自分がされたことをそのままお子さんに・・・さて、
そのような局面において、魁は、
「(特に義務教育においては)あなたの持てる可能性を潰さないため」
「やってるうちにやる気は出る」
「辛い勉強は、いつの間にか楽しくなる(それが本来)」
という3つを軸に答えているのですが、この度、先日さらに高い見識に出会いましたので、その良著をご紹介します。
著者のお名前は・・・・、
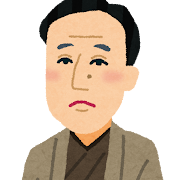 よろしくどうぞ
よろしくどうぞ福沢諭吉先生です!!
タイトルはもちろん、、、、「学問のすすめ」です!
魁の出身大学は立教ですので、(※「みんなの大学情報」様)
- 「箱根駅伝に実に久しぶりに出場する」
- 「長嶋茂雄さん」
- 「魁が在籍していた」
ということでしたら全国区で知れ渡っていますが、大学受験時に福沢先生の慶応大学には全くレベルが達せず、
「なんだかわからんがとにかくスンゲー大学」(含む憧憬)
とだけ感じていました。
*
この度、
「σ(゚∀゚ )オレ、日ごろ学問に関する仕事で生きている時間が多いわけだが、ただ毎日繰り返す作業のようになっていないか??」
的な自らに対する疑問の思いが湧きまして、情報収集をする中で急に入ってきたのがこの”タイトルだけなら誰でも知っている名著”だったのです。
どちらかと言えば、明らかに「学問をススメ」ている魁が、根源であるこの書を読んだことがないのは不一致であると思い立ち、購入を決意しました。
ただし、原著を読み下している時間は取れません。
よって、檜谷昭彦・訳(三笠書房版)の現代語訳版を書店にて購入しました。あるいは、斎藤孝・訳(ちくま書房版)も訳者の先生をメディアで見たことがおありではないでしょうか。
内容は歯切れよく、およそ150年前に出版開始となったとは考えられないほど、指摘が明確です。
福沢先生が切り込んで来られるのは、冒頭からで、
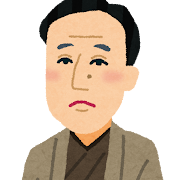 「人に貴賤はないが、勉強したかしないかの差は大きい」
「人に貴賤はないが、勉強したかしないかの差は大きい」とおっしゃっています(訳)。
学問に励み、物事をよく知った者は富み栄え、ムガクなものはその逆である。
ただし同時に、
「(あなたが)知識の問屋でいるだけはいい飯は食えない」
「実生活に役立つ学問を身につけよ」
とおっしゃっています。
お子さんを勉強に仕向けようとするが自身は向学心がなく、経験だけは長いが、評論家的なコメントしかできない役立たず
というのは、恐ろしいことに塾関係者にメチャクチャ多いタイプです。
同時にウソをつくことには長けていて、その場の口八丁手八丁が自分の実力と言い張る。。。(実は破綻していることに周囲は気づいていますが、言わないだけ・・・)
表っツラは良くしようとしますが、すでにどこか違和感がにじみ出ており、早々にガッカリさせられます。
お子さんの「なぜ勉強するの??」に対して、不幸の素になるようなトンチンカン指導を確実に垂れ流しているでしょうから、保護者さんはどうぞご注意を!!!
お子さんを指導する前に、コメンテーターしていないで「学問のすすめ」を全員で読み合わせして、その心を入れ替えなさい!というレベルです。
*
お子さんの「なぜ勉強するの??」に対して、お子さんが実感+共感できる簡潔で最強のひと言を魁は探し求めてきました。
いくら現代語訳された表現とはいえ、
「福沢諭吉がね・・・」
と語ることで、お子さんの行動がバリバリに変わるほど、お子さんが抱えている疑問の感覚は生易しいものではないです。
ただし、今回ご紹介した書籍は、大人の私たちであれば、実感をもって共感することができる一冊(二冊)です。
それを(紆余曲折はあるにせよ)自らの言葉に置き換えて、お子さんに届ける努力は、魁にも、読者さんにもできるはずです!
時代に関係なく通じ、見落としていた分の見識が広がる書であると、この魁、受け合います。
 あ、メタバース全く関係ない記事になっちゃった・・・
あ、メタバース全く関係ない記事になっちゃった・・・



