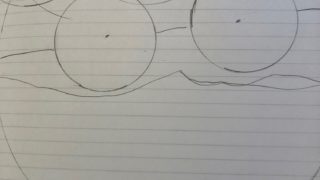前回のこの記事の続きです。(2021年8月)
べべべ、
別に忘れていたわけじゃあありません。
例外なく、全四国民、いや全日本国民待望の「説教テクノロジーシリーズ」です。
2億通超もの「続編はまだか」「完結させないとはどういうつもりか」というおハガキをいただきまして、ついに完結編をお送りします。
さて、
ここに至るまでにヨユーで半年強の時間が空いているので、さすがに「復習」を入れます。
テーマを率直に書くなら、お子さんをどう叱るのか?ということです。
魁はお子さんを指導してきた中で、それはもちろん厳しく叱ったことがあります。
親身だからとか、熱心だからとかではなく、「このお子さんはこのままではいかん」という危機感の下に結果はどうあれ「叱り」を炸裂させてきました。
本当は、「ゲタゲタ笑ってるうちに成績爆上がり」というのが最高の指導のスタイルなのですが、その域に魁は到達しておりませんので。
よって、ゲタゲタさせているだけではお子さん(そしてわざわざ選んでくれた保護者さん)のためにならない場面が登場します。
んで、なるだけならそこまで言わずにスムーズに指導をしたかったが、どうもこのままでは点は取れんし、精神的にも伸びないよな・・・となったら、意を決して叱るわけです。
ただし!その場で感情任せに怒鳴るのは愚の骨頂!(そういう指導者は反省しなさいね)
- 伝えたいことをメモして整理する。(5W1H)
- あなたが塾関係者なら、事前に保護者に伝える。(いわゆる根回し)
- 100%の叱りを発揮する前に、小刻みにお子さんに声をかけ、段々ボルテージを高めていく。(5段階)
という、魁の業務用叱り方手順をシリーズで記事にしていたのでした。
このような長い段階を経て「効果ある叱り」を計画してきた読者の貴方、実は後は簡単なんです。
すなわち、お子さんを何とかしたい!!という思いを込めてフルパワーで怒りを露わに怒鳴る!!
この瞬間だけは後先考えず、全力で叫ぶ!!
の番です。
ただし!
叫び始める前に、あなたにわかっておいて欲しいことがあります。
それは・・・
叱ることについて記事を書いておきながら、意外に思われるかもしれませんが、
「叱ろうとも諭そうとも、相手を変えることはできない」
というのが前提だということです。
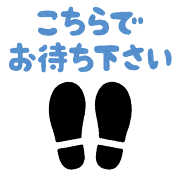 なぜなら・・・
なぜなら・・・この点は、肉親がお子さんを愛情で叱る場合も一緒です。
叫べば変わる、怒鳴れば変わる、、そう勘違いしている人間が特に塾業界の管理職や経営者には頻繁にいます。
いかにも塾らしい。
いつ部下(あるいはお子さん)を怒鳴りつけてマウントを取ろうか??とタイミングをいつも図っているような人物です。
逆説的ですが、すでにその間違った方向で長年凝り固まってしまって成長の余白がないので、もう変わることはないでしょう。
そういった人物は、叫んだことで一時的にスッキリし、自分の中で何かが達成されたように感じています。
残念ながら、スッキリは「錯覚」ですし、ムダに叫ばれた相手は心が離れていくばかりで、不経済ですらあります。
「他人を変えることはできない」の部分については、読者さんが兄弟姉妹と、テレビの見たい番組の時間帯がかぶってしまい、争いになった場面を想像してください。
大人同士であれば、「いいよいいよ、録画や再放送観るから」となりますが、お子さんの時であったらどうでしょう?
何とか相手を翻意させようとし、結局ムリでケンカになったり、半泣きで引くことになっても肝心の放送開始に間に合わなかった・・・という経験はないですか?
観たいチャンネル一つとっても、他人の意志を変えることはひjjjっじょーーーーー!!に(非常に)難しいのです。
一方、
魁がいつも繰り返し記事に書いている文言に、「お子さんは成長性が高いので・・・」というフレーズがあります。
叱る側の指導者も、お子さんより若干生きているだけで、カンペキ超人ではありません。
そんな大人が、お子さんを叱って行動を変えさせ、何とかしようと思うこと自体が傲慢です。
それでもお子さんは、生きてきた時間が短い分、大人たちの発言から吸収して成長する可能性を秘めているので、叱られたことから成長につなげることができるのです。
 逆に誤った叱り方でお子さんの可能性を握り潰すことも可能!!(「栗を全力で握る修行に励むマッチョ」画像はいつも”マッスルプラス”様より!)
逆に誤った叱り方でお子さんの可能性を握り潰すことも可能!!(「栗を全力で握る修行に励むマッチョ」画像はいつも”マッスルプラス”様より!)「そんなこと、子どもでもできるわ!」と理不尽な上司に叫ばれたことありませんか?
その上司はお子さんを舐めすぎです。
お子さんの方が成長性も修正力も高いのです・・・!(ablityでなくpotentialが)
と、長くなってきたので、次回に続きます!(案の定)